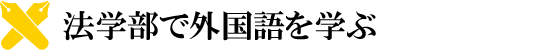教員紹介
Faculty
-
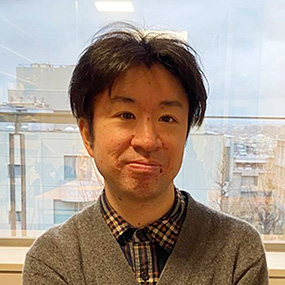
小野 竜史 ドイツ史研究者として過去の人々の生に触れる機会が多いのですが、偶然の出会いによって、人生は本当に大きく左右されるものだと感じます。僕とドイツ(語)との出会いも、まさにそうでした。宮城の石巻出身で「広い世界」に飢えていた―エドワード・ギボン『ローマ帝国衰亡史』の影響で特にヨーロッパにあこがれていた―僕は、履修登録でドイツ語とフランス語で悩んだ末、鉛筆を転がしてドイツ語に決めました。そこからインテンシブや地域文化論の授業でドイツ(語)への関心をかきたてられ、サークルでマックス・ヴェーバーやカール・マルクスの社会理論に引き込まれ、大学院からドイツ現代史と社会理論を専攻して今に至ります。抽象的には「権力と個人の自由」、「社会運動と社会の変化」の問題に関心があり、具体的には西ドイツの兵役をめぐる問題や人々の平和観に対して、1968年の学生運動が与えた影響を研究しています。最近は外国の駐留軍と西ドイツ社会とのかかわりにも関心があります。
ドイツ語圏は文学や哲学、音楽で有名なことは言わずもがなでしょう。例えば「クラシックの音楽家と言えば?」と聞かれて、現在のドイツやオーストリア出身者の名前が1人もあがらない人は、かなりの少数派だと思います。また2度の世界大戦での敗北とホロコースト、社会主義の東ドイツと資本主義の西ドイツへの分断と再統一など、自由や民主主義の問題に嫌でも目をむけさせる、「激動」と表現するしかない近現代史を経験した地域でもあります。さらにドイツについて言えば、日本企業も多く進出する世界3位の経済大国で、EU最大の人口をほこる、ヨーロッパの政治経済の中心の1つです。フォルクスワーゲンの車からニヴェアの化粧品、アディダスのスポーツ用品、エナジードリンクのレッドブル、ハリボーのグミにリンツのチョコレート、「カルテ」や「ムキムキ」といったドイツ語由来の―説がある―言葉まで、日本の日常生活とも意外とかかわりの深い地域でもあります。僕の場合、まったくの偶然の出会いから始まり、現在はライフワークの1つとしておつき合いしているドイツ(語圏)ですが、未だ興味はつきません。そして、AIが日進月歩する現在も、「深いおつきあい」はもちろん、出会いの成否のカギはドイツ語の運用能力にあると思います。
慶應の法学部には、日吉の語学科目や地域文化論から、三田の専門科目やゼミナールまで、学問的にドイツ語(圏)と出会う多くの機会があります。また、恐らくそれ以上に重要なこととして、卒業後も外交官や会社員、研究者としてディープに、あるいは趣味などでよりライトにドイツ(語圏)とかかわる大勢のOBOGがいます。そのネットワークは、大学と学部の枠を超え、広く日本とドイツ(語圏)の社会に広がっています。法学部ドイツ語インテンシブの卒業生として、ドイツ史の研究者として、また―日本とドイツの文化交流をかかげる―日独協会の役員として、ドイツ(語)を学ぶ皆さんとそれらの人々との出会いの場をつくることも、僕の大きな役割だと思っています。そうしたコンタクトに関心のある人は、授業の前後や学生部を通じて、ぜひ気軽に連絡をください!
フットワーク軽く多くの人やモノと出会い、楽しければ身をゆだね、つまらなければ身を引き、嫌なら逆らったり反面教師にするのが、大学生活の醍醐味だと思っています。僕自身、例えばドイツ語よりもロシア語に熱をあげかけた時期もありました。そのため、あくまでも数ある機会の1つとしてお誘いするのですが、法学部でドイツ(語圏)とも出会ってみませんか?僕の方でも、皆さんとの出会いを楽しみに待っています。